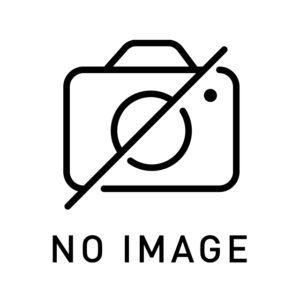ステイクホルダー資本主義
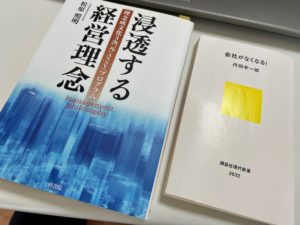
丹羽宇一郎さんの「会社がなくなる!」を再読した。
(私の理解力が足りずなんだかスッキリしなかったので)
日経新聞の記事下の書籍広告で大々的に宣伝されていたので
読まれた方も多いかもしれませんね。
自身の企業経営や国際的な仕事をベースに「日本の将来の見取り図」を描き、
これからの日本を背負う若い人への滋味あふれるメッセージが詰まった良本です。
ふむふむなるほど!といろいろ学べる内容満載ですが、
一番合点がいったのは、アメリカが「株主資本主義」から脱却し、
顧客、従業員、サプライヤー(取引先企業)、地域社会、株主の
5つのすべてに「長期的・継続的」に利益をもたらすべきだとする
「ステイクホルダー資本主義」へ大転換を図ろうとしているという動きを知って
驚いたと、という件です。
※ステイクホルダー=企業の利害関係者
株主第一資本主義の本家アメリカが、
今の経済システムの矛盾(資本主義を支持しない若者の出現等)を発端に、
軌道修正に動き始めたというわけだ。
その動きはイギリス他にも及び昨年2020年の世界経済フォーラム(ダボス会議)の
年次総会でのキーワードはなんと「ステイクホルダー資本主義」だったと!
会社は株主の持ち物ではなく「法人」の持ち物なので、
「法人」の一部である「株」を持っているだけで、
株主だからといって何をやってもいいというわけではない。
(株の売買は出来るけど)
日本でも2000年前後このアメリカ発の
「株主第一事本主義」(新自由主義)にかぶれて追随する企業が続出したけどね。
で、これ「ステイクホルダー資本主義」って日本では当たり前ではないのかい?
古くから「買い手・売り手・世間の三方よし」という
近江商人の経営哲学が根付いているし、自分たちの利益だけを追求するのではなく、
お客様に満足してもらうと同時に社会へ貢献しなければならない、
という「信用・信頼」を軸足とした経営が
数多くの企業で実践されてきたではないか。
もちろんそうでない企業は淘汰されたが。
「ステイクホルダー資本主義」という経営概念は
日本企業の得意とするところであったはずだ。
日本企業はもっと自信を持った方がいいですね。
(本題はココから)そこで、
日本版ステイクホルダー経営を目指した本があったなぁと思い出し、
松原照明さんの「浸透する経営理念」を
事務所の書棚から久しぶりに引っ張り出して読み始めた、というわけです。続く。。
◎丹羽宇一郎さんの略歴
伊藤忠商事の会長・社長、日本郵政株式会社取締役などを歴任の後、
2010年6月から2012年12月まで中華人民共和国駐箚特命全権大使を務め、
同月から早稲田大学特命教授。 日中友好協会会長。
グローバルビジネス学会会長(2021年7月まで)。
※Wikipediaより引用